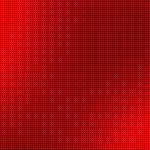「教えるための、また、学ぶための数多い施設を目にし、また、学生や教師たちがあれほど大げさにひしめき合う有様を見れば、識見なり真理なりが人類にきわめて珍重されているように、ともすれば、世の人は信ずるかもしれません。
しかし、ここでもやはり、外観は人を欺いているのです。
教師たちが教える、その努力は知恵のためにではなく、知恵の見せかけと思わせぶりへと向けられていますし、学生たちが学ぶのも知識や識見を獲得するためではなく、おしゃべりが出来るようになったり体裁をつけるためだけなのです。
こうして30年ごとに兎に角、新しい世代が世の中に出てはきましたが、彼らはまるっきりの知恵なしで、ただ、数千年を通じて集められた人間の知恵の成果を本の概略だけ大急ぎでむさぼりくらい、すぐさま、過去の一切の人々よりもはるかに賢くなろうと考えます。
こんな目的で、彼らは、あちこちの大学に籍を置き、さまざまな書籍・・・自分の同時代者か同年配者としての最新の書籍へと手を伸ばします。
ただ彼らの読む全ての書籍は、簡単で、彼ら自身が新しいように、新しくなければなりません!
それから、彼らは、それらの書籍をよりどころとして、だらしの無い判断を下します。
ただ物知りになることだけを心がけるばかりで、洞察する見識を求めようとは考えていません。
ものを知っているということは見識に達するひとつの単なる手段ににすぎず、それ自身としては、ほとんどあるいはまったく価値のないものであることなどは、彼らの思いおよばぬところ、実は、このことこそ、哲学的頭脳を有するものにして始めて気がつく考え方なのです」
一寸長い引用になったが、哲学者ショーペンハウアーの小論文集(1851)の1節である。
当然、当時のドイツにおける社会現象の痛烈な批判となるものであろうが、しかし、何か最近のわが国のことを言っているようでもある。まさに、今日の我が国がかかえる教育問題への批判であるともみえるのだ。
論文が翻訳され刊行されるまでの115年、つまり、昭和41年(1966年)は我が国にとっては「マス・コミニケーシヨン」が盛んに言われはじめたころでもあるのだが、翻訳者をして「いまだに新鮮な感銘を受ける。いや、それどころか、まるで現代人のためにわざわざ用意されて書かれてあった」のではと言わしめていることだ。
そして、その言葉は、更に、その50年後のいまも通じることでもある。
ペシミズムといわれる哲学的考察も、率直で辛らつな言葉も、そのまま現代社会に生きており、人の歴史は繰り返されていることを示す証左であり大変興味深い。
このほこりまみれの文庫本は江古田から、この所沢キヤンパスへ移転した際に運び込まれたダンボール箱から取り出されるまで、すっかり忘れていたもの、多分、若い頃に神田の古本屋街で買ったものだろうが・・・。
**
日々のテレビや新聞報道によるニュース・・・。パソコン、雑誌などによる雑多な情報の氾濫、グローバル化は、ショペンハウアーの生きた当時のそれをはるかに越えるものであれば「洞察する見識」、「自ら考えること」の必要を痛感はしても、極めて困難なことと言わざるを得ないもの・・・。
しかし、近年のわが国における教育の空洞化をみるとき、「生きること」、「学ぶこと」の意味、その「本質」を「みずから考える」時間を持つべきであり、いま何より重要なことなのだと思わされることでもある。
ところで、先日の日本経済新聞には識者による寄稿文が掲載されていた。
「1980年代、158万人だった18歳人口は1992年の第2次ベビーブーム世代によって205万人にふくれあがり『受験合理主義』、学習の質を変えた合格偏重主義が台頭したのだという。
授業の終わりには、「何か質問は・・・」と問うが、ほとんど答えが帰ってくることはない・・・。
「変な質問をしたら恥ずかしいから・・・」というよりは、「聞いてなかった」「興味が無い」「質問が分からない・・・」「・・・・・!」
或いは、今の若者にあるといわれる「知ってる、つもり・・・」「わかった、つもり・・・」という、「わかったつもり」症候群・・・?
なにかに追われるように先へ先へと虚ろな眼を向け、咀嚼する時間を持たないのだ・・・。
いまどきの大学生、わからないのは当たり前という社会的な風潮もある。その甘やかしが若者を駄目にしたのだと言う識者は多い。
しかし、そんな甘えの空気は行き渡っており、だから、恥らうこともない・・・。
知らなくともなんとかなるのではという安易さ、甘えの無気力がみえる。
とにかく、以前には大学の入試があったにも関わらず「正解発見型の授業」があり、「本質を探求する教育があった」のだ、ともいうのだが・・・。
目標を見失った当事者たちが、やがてまた、教育の様々な場に立つて指導する事になると、その本質はますます見失われ一層の混乱を引き起こすことになるのだろう。
**
「多く読んだり学んだりすることが、みずから考えることを妨げるのと同様に、多く書いたり教えたりすることは、人間から知識や理解を明瞭にし、根本を見きわめる習慣を奪います。というのは、時間がその人に明瞭かつ根本的な知識及び理解を獲得することを許さないからです。と言う文章には常日頃の私自身が考えさせられていることでもある。
「非常に多くの知識を持っていても、それが自己の思考ですっかり咀嚼されていないならば、はるかに少ない知識でも幾たびか繰り返し考え抜かれたものに比べると、その価値は著しく劣るでしょう。
なにしろ、人は、自分の知っていることを、あらゆる方面から組み合わせてみたり、ひとつひとつの真理を他のそれぞれの真理と比較したりすることによってのみ、初めて自分自身の知識を完全に我がものとし、また、その知識を自ら活用出来るようになるのですから。
人はただ自分の知っていることだけを熟考してみることが出来ます。
それゆえ、人はなにごとかを学ばねばなりません。
とはいえ、人が知っているのは、やはり、みずからすでに熟考を経たものだけに限られます」という。
「みずから考えること」の、この部分には若い頃のわたし自身が強く考えさせられたものでもあり、時間を見つけて当時の社会、ドイツ、そして日本の教育事情などと併せて、改めて読み返してみたいと思っている。
(28 Nov.’07 記)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
注:ショーペンハウアー 独・1788~1860 ペシミズムの哲学者。カントとプラトンの研究に没頭し、1813には「根拠律の四根について」を書いている。またゲーテの「色彩論」に刺激されて「視覚と色彩について」を書いた。
主著は「意志と表象としての世界」、そのなかで「世界」とは「私の表象」にほかならず、その根源は非合理的な生への盲目的意志であるという。この意志としての世界はみたされない欲望を追求するものであるゆえ、あらゆる苦悩の根源になる。生とは苦痛だ。その生の苦痛から解脱するのは、意志を否定し、禁欲と静寂、涅槃(ねはん)の境地に達することだと説いた。彼の哲学はニーチエやワグナーに強い影響を与えている。